「地域おこし研究員」制度をご存じでしょうか。「地域おこし協力隊」に似ていますが、こちらは慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の大学院政策・メディア研究科に設置された「社会イノベータコース」と、全国各地の11の自治体・団体が連携して取り組んでいるプログラムのこと。学生は「地域おこし研究員」として自治体・団体に任用されて地域に住み込みますが、SFCにも通ってみっちりと授業や課題などで鍛えられたり、現地でも遠隔の授業と指導を受け続けたりしながら、現場で実践と研究を行い、自ら成長しながら、地域を変える成果を実現していきます。
地域課題に取り組むプロを育てるためにつくられたという、この仕組みはどんなものなのでしょうか。慶應義塾大学総合政策学部教授の玉村雅敏さんと、実際に活動している大学院生のみなさんに伺いました。
玉村雅敏さん(慶應義塾大学総合政策学部 教授)
専門分野は、公共経営、ソーシャルマーケティング、評価システム設計など。
慶應義塾大学総合政策学部卒業。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科、千葉商科大学助教授、慶應義塾大学総合政策学部准教授を経て現職。博士(政策・メディア)。
主な兼職(現職)として、内閣府官房地域活性化伝道師、総務省地域力創造アドバイザー、JICA業績評価アドバイザー、横須賀市政策研究専門委員、天草市・鈴鹿市・市原市・長島町・大崎町・大山町・東川町・鹿児島相互信用金庫などのアドバイザーなどを務める。
「地域おこし研究員」とは?
「地域おこし研究員」になるにはどうすればいいのでしょうか。この仕組みは、SFCの「大学院生」と、地域に任用される「研究員」の2つの立場を持つことになります。まず、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科に出願して、大学院の入学試験に合格しなければなりません。そして、SFCと連携している自治体や団体での「地域おこし研究員」にエントリーして、それぞれの審査を受けて、任用されることも必要です。うまくタイミングを合わせれば、入学と同時に地域おこし研究員として活動することもできます。また、入学してからの任用や、先に連携地域で任用されて活動をしてから大学院に入学することも可能です。
自治体や団体に任用されると、それぞれの規定に従って、現地での活動やSFCと行き来することや、各地の調査研究を行うことを想定した活動費と、現地で生活することを想定した報償費などが出ます。
大学院1年目の春学期は、主にSFC側にいて、地域とも行きしながら、プロジェクト開発を行います。この時期は、大学院では、授業や課題、グループワークなどで鍛えられる時期にもなります。慶應義塾大学では大学院生なので、大学院のトレーニングを普通にします。ちなみに、SFCの大学院の授業は、時間外にたくさんの本を読んで課題に取り組んだり、グループで検討したりしたものを持ち寄ってくることになるので、時間外にかなり取り組まないと意味がないものになります。
それ以降の時期は、地域の現場で実践的に活動をしますが、授業も受け続けることになります。それは、対面でのものもありますが、各地を同時につなぐ遠隔授業でも開催します。他には、SFCや都心サテライトで定期的に行われる研究ミーティングや授業で指導を受けて、同級生とグループワークなどの授業課題などにも取り組みます。
また、こまめに地域おこし研究員のWebミーティングをしたり、相互に訪問するなど、各地で活動する地域おこし研究員同士も、相互に影響し合って研究や思考、プロジェクトを深めていくことも行います。
現地活動と学習が並行してできる「地域おこし研究員」。そもそもどのようなきっかけで、またどんなことをめざして生まれた制度なのでしょうか。まずは基礎的なお話から伺うことにしました。
 慶應義塾大学総合政策学部の玉村雅敏さん
慶應義塾大学総合政策学部の玉村雅敏さん
玉村さん「慶應SFCでは、社会に対して問題意識を持ち、行動し続けることが普通で、実践を通じて自ら理論や学問を創り上げていく実学も重視しています。学生たちは、現場での経験は力になることを知っているので、たとえば長期休暇ごとに、どんどん社会課題の現場で動き回っています。学生によっては、休学をして、海外や地域で時間を掛けた学びに取り組んでいたりします。そういったことがSFCでは普通なのですが、特に大学院はプロを鍛えるところなので、そういったことをもっともっとやりやすくすることを、地域とも連携してやれないか。また、遠隔と対面を組み合わせたやり方で実現できないか。そんな考えから生まれたのが、大学院生でありながら地域の一員として研究・開発ができる「地域おこし研究員」です」。
SFCは、グローバルにインターネットの研究開発をリードしてきた本拠地でもあります。20年近くインターネット上で大学の授業を提供したり(※1)、アジア圏に向けたインターネット講義配信も行われているだけに、現地での活動と遠隔授業を同時に実現する仕組みが実現されたのも納得です。
※1 SFCグローバルキャンパス(SFC Global Campus)のこと。詳しくはこちら
玉村さん「地域おこし研究員は、SFCの大学院に所属して活動することにも理由があります。私はSFCの卒業生なのですが、私が学生だったころから、SFCの大学院政策・メディア研究科はプロを育成する「プロフェッショナルスクール」だと説明していました。プロフェッショナルスクールというと、例えば、ビジネススクールやロースクールなどをイメージされるかと思いますが、SFCでは、アカデミックな研究を徹底的にやることでプロを育成することができると考えています。研究をどう考えるかにはいろいろな考え方がありますが、1つの考え方として「先端(フロンティア)」で「創造(クリエイティブ)」すること、と考えてみると、まず、どこが「先端」なのかを自ら設定できることが必要になります。そのためには、やみくもに、もしくは曖昧に、何かを根拠なく主張をするのではなく、まず、根拠もロジックも詰めて、研究テーマを意味があるものとして設定することが必要になります。そして、その領域やテーマに関することは徹底的に勉強も調査もして、たとえば、過去の事例や実践を検討して、先人たちの挑んだ課題や成果も理解する。さらにそこから得た知見を整理して、どこに「先端」があるのかを伝えることが必要になります。そして、そうやって示した「先端」において、自ら研究成果を「創造」して、意味があることを示していくことになります。
そういった営みが社会を前進させてきたのですが、それをやれる人がプロであり、そのためにアカデミックな研究でのトレーニングをするのがSFCの大学院だということです。
そして、そういった試行錯誤をするチャレンジ精神に溢れた大学院生が地域に住み込んで地域のためになることを研究する。そのプロセスでは、たくさん悩みも持っています。研究員が地域の仲間として住み込んでいるので、ちょくちょくと、地域の皆さんも一緒に考えてくださるようになります。そうすると、より本質的に何が地域に必要なのか、何か課題なのかなども、地域の方と一緒に探り出していくことにもなっていきます」。
玉村さんは、以前から、地域おこし協力隊として赴任した卒業生や、地域で挑戦する卒業生などの相談に乗り、その支援や助言をしてきたことが大学院での研究指導と似ていて、大学院のトレーニングを受けるとより効果的になる、と気付いたことが大きかったと語ります。彼らの学びの形は、いわば「リサーチャー・イン・レジデンス」。アーティスト・イン・レジデンスのように地域に入り込み、日常的に関わっていくことで地域の本質が見えてくることが強みです。
実践と研究の相乗効果を追求する、地域おこし研究員の仕組み
名称が似ているとおり、「地域おこし研究員」は「地域おこし協力隊(※2)」の1つの工夫として始まったものでした。そもそも、地域おこし協力隊は、挑戦したい人が地域に入り、地域活性のための活動に取り組む制度。そのときに、地域に住み込みながらも大学院でも活動できるようにするのも意味があると考え、そういった発想に共感して、大学院生と一緒に試行錯誤できる地域と慶應SFCが連携して取り組むことになりました。そのアイデアを一緒に考えた地域であり、最初にはじめた地域が鹿児島県・長島町でした。その後、徐々に、そのネットワークは広がってきました。
※2 多くの地域で使われる名称「地域おこし協力隊」は、あくまで総務省の定義。その名称や役割などは基本的に自治体が自由に決めることができ、たとえば、岩手県釜石市は「釜援隊」、長崎県対馬市は「島おこし協働隊」、鳥取県大山町などでは「地域おこし研究員」を採用。
目の前に現場がある状況で、各地の研究員や大学院生がともに学べば、実践も研究も広がりが生まれ、個々で活動するより深く課題に取り組めるようになるはず。例えば「ソーシャルファイナンス」の授業ひとつ取っても、社会活動のための資金調達など財源を確保する思考や方法を学びながら、それぞれの現場の状況などを念頭に様々な授業課題に取り組み、指導や助言を受け、他の人の意見を聞くことや、相互にアドバイスをすることもしているといいます。
そして現在では、自治体や信用金庫の職員なども、組織の制度を工夫して「地域おこし研究員」として活動を始めているのだとか。また、地域に赴任する地域おこし研究員にならなくても、そういった方々との学びをともに進めたいと、幅広い分野からの入学も増えているのだそう。SFCの先進的な取り組みに注目する自治体や団体、企業が多いことが伺えます。
玉村さん「鹿児島相互信用金庫や岩手県の花巻市は、実践型のシンクタンクとして組織内に「地域おこし研究所」をつくって活動しています。この2つの組織では、それぞれ数人の研究員がいますが、そのうち、大学院での学びが意味があるテーマの方が、SFCの大学院に挑戦して入学して、大学院にも所属して指導を受けながら研究に取り組んでいます。地域おこし協力隊だけではなく、職員についても、地域活性に取り組みたい気持ちがあり、価値があるテーマの設定ができるのであれば派遣できる制度を新設してくださいました。
鹿児島相互信用金庫は、私が長島町のアドバイザーとして、井上貴至副町長(当時)や皆さんと一緒に「ぶり奨学プログラム」を開発した際に、一緒に取り組んでいただき、その根幹となる「ぶり奨学ローン」をつくってくださったのですが、この経験を通じ、金融機関が地域活性化に取り組む可能性を見つけたことがきっかけとなり、「地域おこし研究所」と「地域おこし研究員」に取り組もうと考えたとのことです。信用金庫の役割である、地域の中小企業を支援する地域密着型の仕組みや制度をつくりたいという職員が入学し、活動しています」。
「答えが決まってない課題に取り組む」自治体とともに
現在、「地域おこし研究員」は、全国11の自治体や組織が、SFCと協定を結び、連携して推進をしています。それぞれの地域からは、地域おこし研究員に「これをやって欲しい」というお題を提示するのではなく、提示されているのは地域の特性や現状の活動、テーマの方向性。そこから、学生本人が自ら研究や調査活動を通じて、課題を設定し、挑戦をしていく。実際に動き、学び、研究をし続けると、徐々にテーマも変わっていく。それこそが期待していることでもあります。
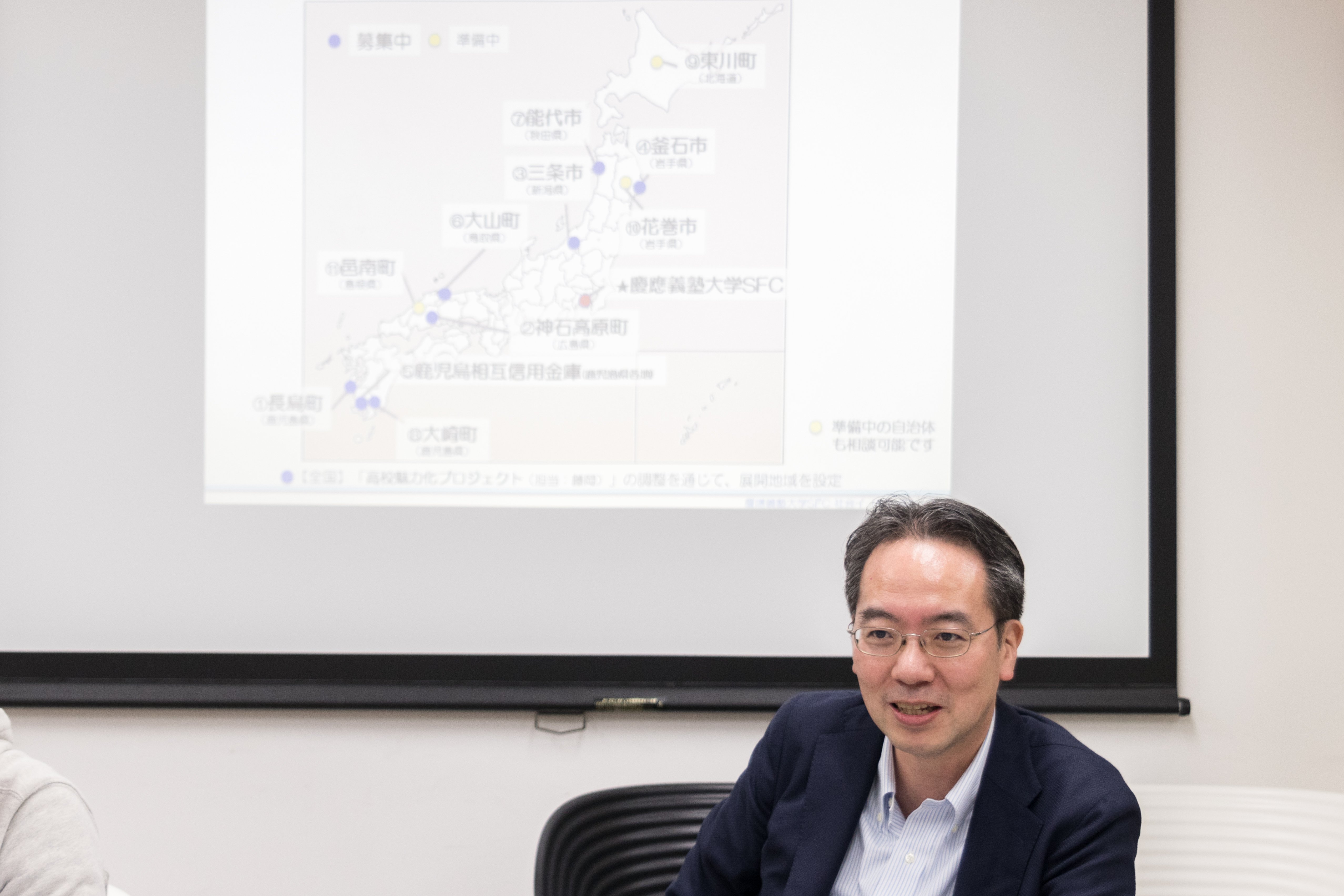 11の連携地域
11の連携地域
玉村さん「すでにやるべき課題が明確で、『これをしてほしい』という答えが見えているのであれば、経験も実績もある、その道の専門家が取り組む方がいい。かたや、試行錯誤しながら、様々な人とともに課題の本質を追求するからこそ見えてくる『答えが決まってない課題』に取り組むときには、学び続ける大学院生だからこそできることがたくさんある。その際に、SFCのような幅広い分野の教員たちと相談をし続けながら、学生が活動をすることで、より効果的な活動や成果が実現しやすくなります」。
 静岡県で小学校教諭として勤務後、政策・メディア研究科に入学した中川優芽さん。修士課程2年生の現在は、釜石市の地域おこし研究員として災害教育を研究中。県内のテレビ局の密着取材を受けたそう
静岡県で小学校教諭として勤務後、政策・メディア研究科に入学した中川優芽さん。修士課程2年生の現在は、釜石市の地域おこし研究員として災害教育を研究中。県内のテレビ局の密着取材を受けたそう
高校魅力化プロジェクトを高校生自身が進めるために、高校生によるドローンアカデミーづくりを開発・実践した広島県・神石高原町の地域おこし研究員。スポーツのまちづくりによる地域活性の仕組みづくりを開発・実践した新潟県三条市の地域おこし研究員。地域密着型の金融機関の役割を追求する地域おこし研究員など、テーマや内容は確かにさまざま。また釜石市では、静岡県で小学校の教員をしていた中川優芽さんが地域おこし研究員として赴任し、現在も防災教育の研究を続けています。
その他、超地域密着・住民参加型テレビ番組の「大山チャンネル」の活動や「楽しさ自給率No.1」を目指した活動などが充実している鳥取県・大山町など、どの地域も答えが決まってない課題に対峙しようというチャレンジ精神に溢れた自治体。だからこそ、学生側もともに取り組む面白さが感じられると言えます。
地域おこし研究員の研究と、彼らならではの強み
同席した学生のみなさんからも、それぞれ活動と現状を聞きました。一人目は、松浦生さん。大学在学中から人口3,500人の鳥取県鳥取市の用瀬町で同世代向けシェアハウス運営と地域活性プログラムを提供する「もちがせ週末住人」を運営してきました。
 大山町「地域おこし研究員」の 松浦生さん。学部生時代には、鳥取市の用瀬町で「もちがせ週末住人」を運営
大山町「地域おこし研究員」の 松浦生さん。学部生時代には、鳥取市の用瀬町で「もちがせ週末住人」を運営
松浦さん「同世代に人の繋がりを通じて豊かさを感じ、さまざまなことに挑戦してほしいと考え、地元暮らしが体感でき、挑戦してもらえるような拠点や仕組みづくりを用瀬で行ってきました。大学院では、この経験も活かして、鳥取県の大山町での挑戦として、大山町にとっても参加者にとっても意味があるプログラムをさらに創り上げていきたいと考えています」。
また松浦さんは大山町の「楽しさ自給率No.1」戦略をベースに、地域の子どもたちがやりたいことを叶えるための支援ネットワークづくりも進めています。大人に見守られて育つことで、県外に進学した子どもたちが地元に戻るような人材サイクルとなれば、と語ります。
玉村さん「SFCの大学院の学生には、松浦さんのように経験を積んできた人も大勢います。SFCの大学院は、入学前から準備してこないと厳しいところです。大学院の入試では「研究計画書」を提出しますが、その際には、これまでの経験のもとで、改めて大学院で挑戦したい研究テーマをまとめあげることが必要です。そういった準備をした状態で大学院に入ると、大学院でのさまざまな授業や課題、刺激などを通じて成長が見込めます。実際には、入学後に様々なことを学び続けるので、テーマは変わっていきますが、それも意味のあることです。
地域おこし研究員は、大学院に入る段階で地域や現場が決まっているというのも強みになります。大学院に入ってから研究内容を検討し、地域にアプローチをかけると、場合によっては、修士課程の2年間ではタイムアップになることもありえます。一方、地域おこし研究員とともに活動しようという自治体は、すでに協力する前提であり、活動費の確保や、地域の活動基盤もあり、2年間をより有意義に過ごすことができます」。
研究テーマや意義、目的は、自ら問題意識を持って調査・研究してこなければ見つけられません。入学時は、個人の資質はもちろん研究テーマとそれに対する準備、2年後の可能性まで厳しく審査されるとのこと。「地域おこし研究員」はこのハードルを乗り越えてきた学生たちだからこそ活きる仕組みなのです。
太田良冠さんは、地域おこし研究員の第一号。飲食系コンサルタント企業で働いたのち鹿児島県・長島町の地域おこし協力隊に応募、一年間、協力隊として活動した後に大学院にも入学しました。
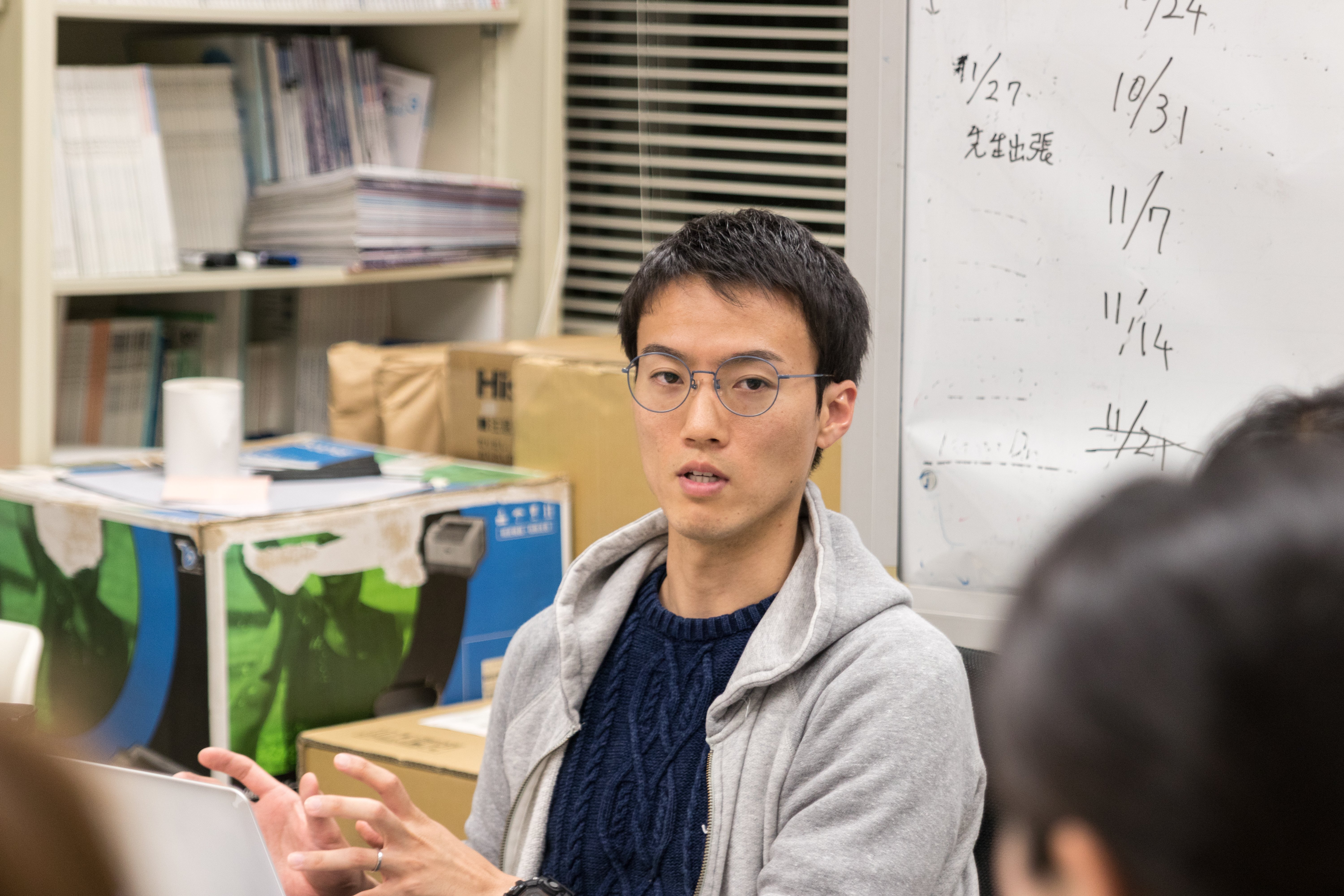 長島町「地域おこし研究員」の太田良冠さん。シェフツアーやアンテナフードトラック仕組みづくりを推進中
長島町「地域おこし研究員」の太田良冠さん。シェフツアーやアンテナフードトラック仕組みづくりを推進中
太田さん「地域おこし協力隊として生産者と消費地のシェフたちを繋ぐシェフツアープロジェクトを立ち上げ、ある程度の成果を出すことができました。地域住民との合意もでき新たなコミュニティづくりも成功していますが、すべて実践で得たことでした。この成功の理由を理論的に整えて、効果的な仕組みづくりをしていきたいと思い、地域を離れず学べる方法を探していた時に制度ができたんです。消費者と地域産業の繋がりが浅いという課題や、地域支援をしたいというシェフの話がプロジェクトの発端でしたので、今後も消費者と生産者をいい形でつなぐ役割になれればと考えています」。
太田さんの場合は、現地で経験を積み、さらに自分の経験を裏付けながら、効果的な仕組みづくりをするために入学したというわけです。現場で活動しながら研究できるメリットがあるため、自分に必要な学びを徹底的に追求しようという人にも、地域おこし研究員はいい制度なのだとか。
玉村さん「フィールドワークが必要な研究は検証に適した地域探しが大変ですが、その意味でも全国各地の11の連携地域があることで多様性が得られます」。
 岩手県「地域おこし研究員」の吉田真彦さん(市職員)。伝統芸能の神楽に地域の一員として関わり続ける関係人口づくりに取り組む
岩手県「地域おこし研究員」の吉田真彦さん(市職員)。伝統芸能の神楽に地域の一員として関わり続ける関係人口づくりに取り組む
吉田真彦さんは、岩手県花巻市地域おこし研究所所属の研究員。小さな頃から大迫(おおはさま)地域の伝統芸能で重要無形民族文化財の神楽を学んできた踊り手であり、今は継承者として若い世代に指導も行っています。
吉田さん「今の保存会には若い人がほとんどおらず、5年後には踊り手がいなくなる可能性があります。大学院では、神楽の継承と人口増に繋げる仕組みや方法を研究できればと思っています。これまでの大迫住民しか関われない仕組みを変え、フレキシブルに神楽の勉強や技術が学べるようにして関係人口を増やし、地元保存会と融合させて神楽を維持保存するのが理想です」。
今後の研究項目は山積み。だけど、まずは興味のある人が気軽に体験できるような窓口づくりができたら。そして神楽を絶やさず今後にきちんと伝えていきたい、と目標を語ってくれました。
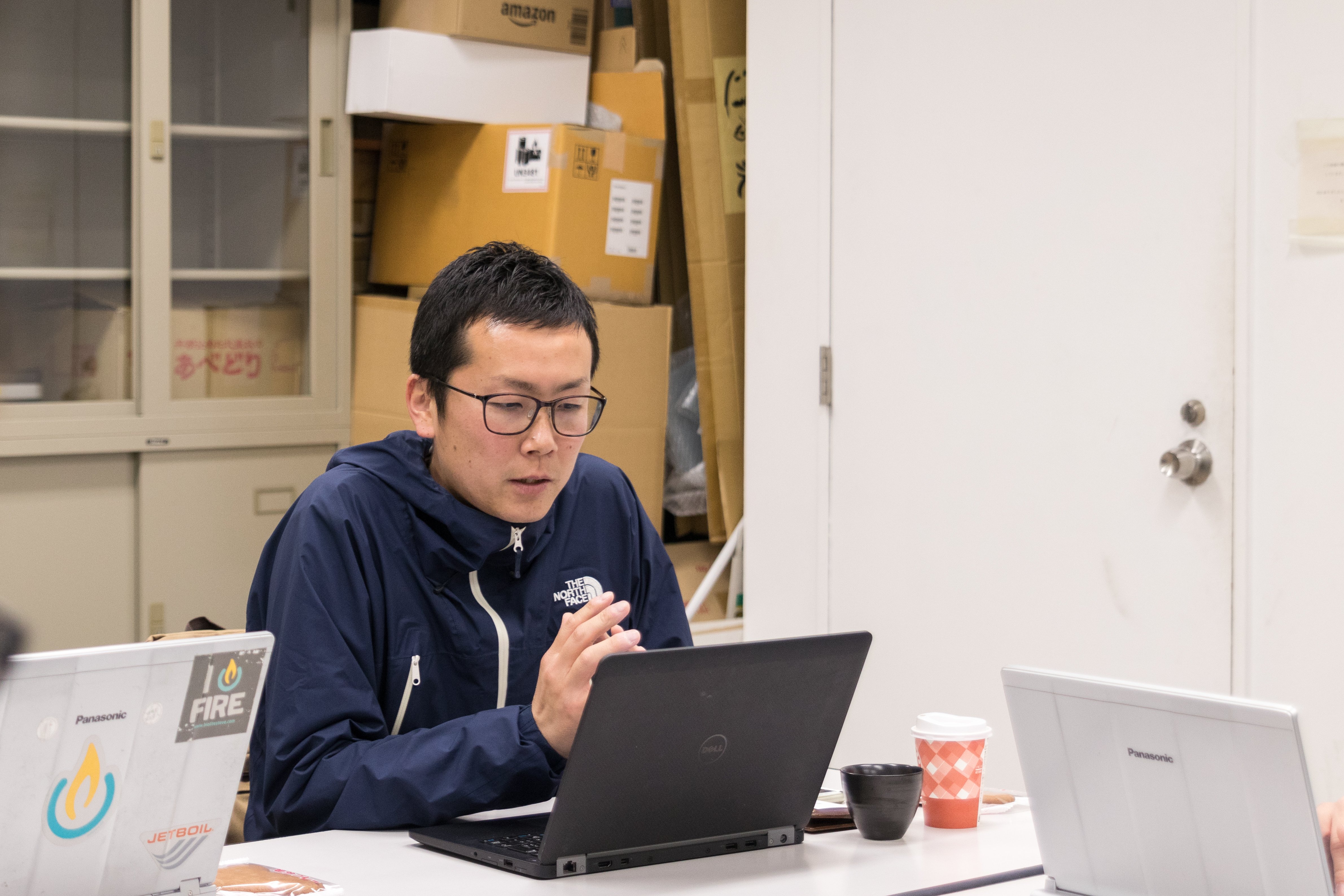 大崎町「地域おこし研究員」宮下巧大さん(町職員)。大崎町は「リサイクル率日本一」のみならず、日本一食べられている鶏肉や、コンビニエンスストアのおでんの大根を提供している、“じつは”すごいものが多いまちです
大崎町「地域おこし研究員」宮下巧大さん(町職員)。大崎町は「リサイクル率日本一」のみならず、日本一食べられている鶏肉や、コンビニエンスストアのおでんの大根を提供している、“じつは”すごいものが多いまちです
最後は、宮下巧大さん。人口13,000人の鹿児島県・大崎町役場企画調整課の職員です。大崎町は20年前からリサイクルを始め、155の衛生自治会がコツコツと分別を続けてきた結果、リサイクル率82%で、12年トップのリサイクル率日本一のまちに。第2回「ジャパンSDGsアワード」でも内閣官房長官賞を受賞しています。
宮下さん「焼却炉の導入よりゴミが削減でき、収益にも繋がるシステムと認められたことで、大崎町はJICA経由でインドネシアにリサイクルの技術指導に行っています。そこで、この優れたリサイクルシステムを世界的に認められるものにするには、何をすべきか。またこのシステムは住民主体の衛生自治会が運用していますが、リサイクルを推進するとコミュニティにはどんな影響があるか。こういった要素を検証した上で、リサイクルシステムを導入した地域に満足してもらい、よい評価をしてもらえるような仕組みができないかと考えています。
またリサイクルの効果や結果を可視化し、より楽しく続けられるポイントシステムなどもできたらベストと言いつつも、入学前に設定したテーマとはかなり変わっているんですが……と苦笑する宮下さん。
宮下さん「入学してから毎日新しい知識が入ってくるので、その知識を頭のどこに収めようかと考えるだけでも大変で。でも、毎日の変化があることで、研究をより具体的に検討していけそうな気がしています」。
前提が見えては変わっていくのは、刺激を受けていることの現れです。変わっていくことはむしろ当然。学びながら未来へと繋げる仕組みを考えることは非常に意味があること。同様にテーマを育て続けている、花巻市「地域おこし研究員」の高橋誠さんも含め、本当に真摯に取り組んでいることが言葉からもわかります。そんな彼らも現場と大学とを行き来しながら活動を進めていきますが、その際に学び続けられることはどんな強みになるのでしょうか。
玉村さん「大学院で学び続けていると、発見や知識も増えていき、見えることが広がっていき、テーマも進化していくはずです。逆に言うと、視野が広がるようなことをし続けていくことは大切。例えば、自分が注目する領域をうまく設定して、その関連事例はすべてみることは大学院の研究では当たり前です。あとは、「何が分かったのか」の結論を示すだけではなく、どのような「仮説」のもとで、どういった「プロセスを設計」してみて、どうだったのか、そういったことをいつも確認し続けながら、自らの研究を育てていくことも大切です。そういった学びのプロセスを持ち続けるのがSFCの大学院での活動です。また、SFCの大学院では、授業は基本的には自発的に学び、活動している前提で行われます」。
対話していると、学生がやろうとしたこと、やったけどできなかったこと、やったことで気付いた別のアイデアなども徐々に見えてくるそう。彼らの取り組みは自分にとっても勉強になる、とも。
玉村さん「学生全員がパートナーです。みんな好奇心の塊ですから、彼らの発言にもヒントになることがたくさんあるんです」。
たくさんの物事を見て興味を持ち、みんなに伝えたいと思う。そんな好奇心のスイッチも入りやすくなる刺激に溢れた土壌こそが、未来の地域活性のリーダーを育てる力にもなっているのかもしれません。
離れていても、切磋琢磨できる場所として
 シェアハウスで暮らす3人。勉強も日常もほぼ一緒
シェアハウスで暮らす3人。勉強も日常もほぼ一緒
じつは現在、吉田さん、宮下さん、松浦さんの3人はシェアハウス暮らし。二拠点居住は大変だろうと、玉村先生から提案されたのだそうです。地域おこし研究員として学ぶ3人は、科目や課題も近いため「24時間ほぼ一緒」。
玉村さん「本当は、SFCのそばに、まちづくりに関わりたい人全員が住めるシェアハウスがあればいいんですけどね。寝食や宿題だけでなく、一緒に過ごすことで刺激しあって、よりそれぞれの地域のことが見えることにもなると思うからです。SFCには滞在型教育研究施設があります。似たテーマを持つ人が身近に暮らしていることの影響は大きいですよ。学部生も地域から来た大学院生がそばにいれば、事細かに実際に話を聞いたり、一緒に考えたりすることもできますよね。3人のシェアハウスは今後に先駆けての実験みたいなものですが、少しずつ、仕組みができていければいいなと思います」。
地域の課題を、自分の持つ知見を生かして解決していきたいと語る学生たち。その静かに燃える思いには、終始感心させられっぱなしでした。在学中はもちろん、卒業後の彼らが地域に何を生み出すかまでも気になる「地域おこし研究員」制度。地域活性の新たな活動の形として、末長く追いかけて行きたいものです。
文 木村 早苗
写真 池田 礼

